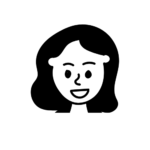最低限で大丈夫。後悔しない出産準備リスト【2025年版】
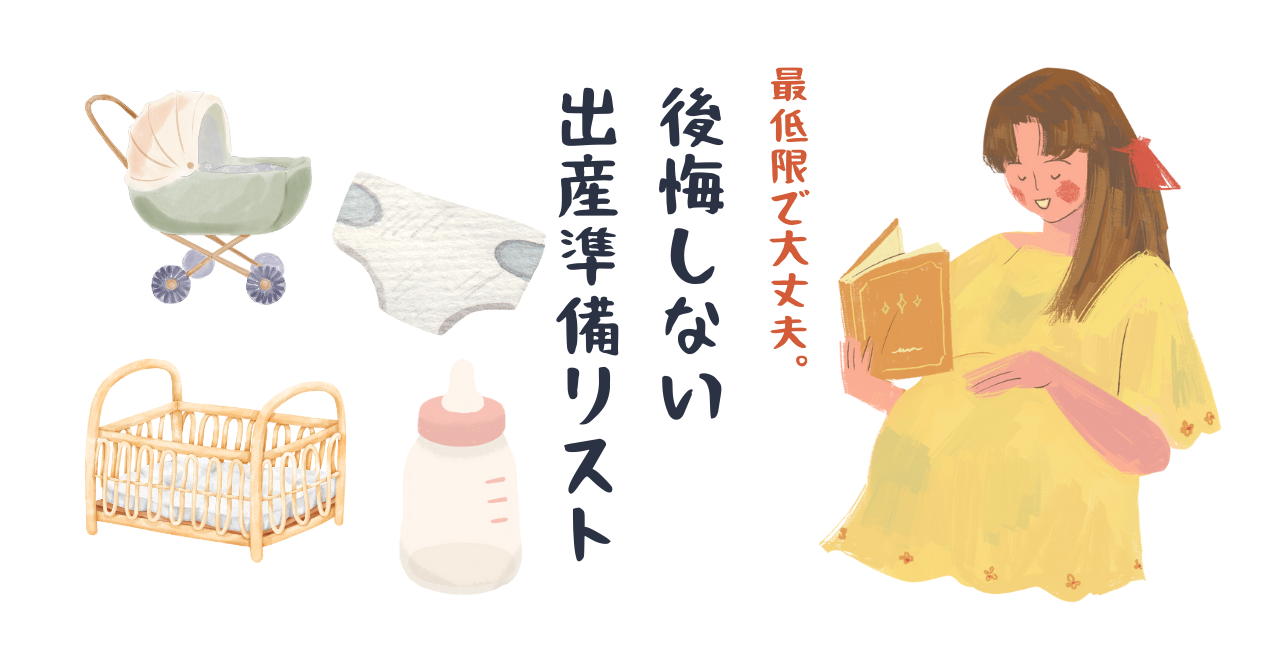
※この記事は、アフィリエイト広告を利用しています。
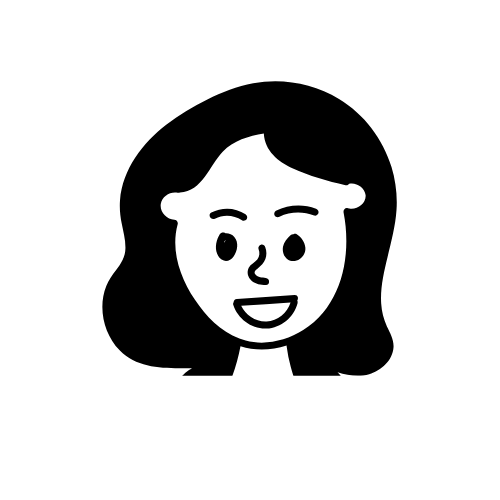
初めての妊娠。
出産準備リストを見ても、正直、
何が何だか分からない。
イメージが沸かない。
一体これって何に使うんだ。
そして、どこに売ってるんだ…。
私自身、1人目の時にこういう経験をしました。
産まれたら出かけられないし、「今のうちに買わなくっちゃ」
無かったら困るかもしれないから、「今のうちに買わなくっちゃ」
何に使うかよく分からないけど、「今のうちに買わなくっちゃ」
と、よく分からない不安にかられ、
「今のうちに買わなくっちゃ」病を発症していました。
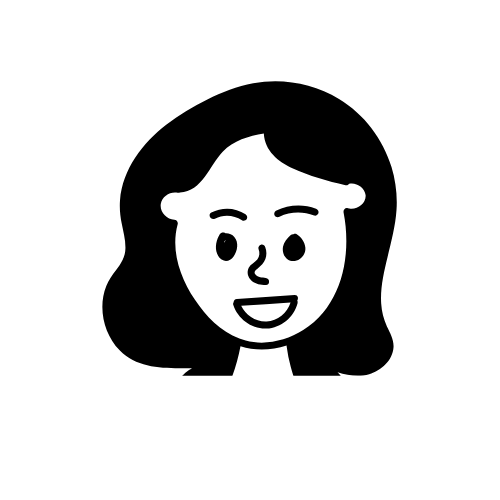
「過去の自分よ……」
「これは、今買わなくても大丈夫だよ」
と、言ってあげたいくらい、使わなかったものがありました。
そこで今回は、
「必要最低限で大丈夫。私流、出産準備リスト」
を作ってみました。
ただでさえ、お金がかかる赤ちゃん用品。
すべて、買い揃えようとするものならば、お金はいくらあっても足りません。
ですが、何が必要で、何が必要ないか、調べてみてもよく分かりませんよね。
そして、
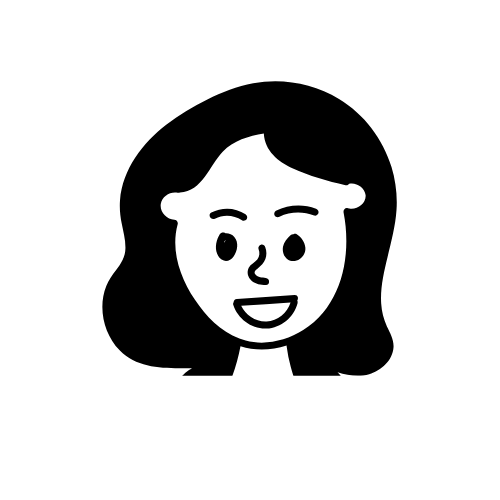
「買ったはいいものの、大して使わなかった」
なんて、私のように後悔してしまいます。
私のような思いをしないよう、これから初めて出産を迎える妊婦の皆さん。
参考にしてみて下さい。
産まれる前に必ず必要なもの 17選

最初に、出産前に必ず準備しておいた方が良いものを紹介します。

新生児 肌着
新生児肌着とは、産まれたばかりの赤ちゃんでも着られる肌着のことです。
サイズは50~60cmで売られていることが多く、生後5~6ヶ月くらいまでは着用できます。(赤ちゃんの大きさや成長度合いによっては、それ以降も着用できます。)
新生児期(産まれてから1ヶ月間)の場合は、季節問わず、
「短肌着(たんはだぎ)」と「コンビ肌着」のセットで着ることが多いです(セットで販売されていることが多いです)
特に夏は暑いので、家にいるときは、肌着のみで過ごしていました。
我が家は、3人とも「短肌着」は生後2ヶ月程度、「コンビ肌着」は生後6~7ヵ月程度まで着用していました。
「短肌着」は、裾が腰までの短めの肌着のため、オムツを交換する際は便利です(いちいちボタンの着脱をしなくて良いため)
ただ、動きが活発になってくると、はだけてしまいます。オムツ丸見えです。
一方で、「コンビ肌着」は、裾が膝まであります。股下にスナップボタンがついているため、はだけにくいです。オムツもすっぽり隠れるため、なんとなく安心感があります。
我が家は、「短肌着」は3~4枚程度、「コンビ肌着」は5~6枚程度、購入しました。
上記以外にも、「長肌着(ながはだぎ)」があります。
「長肌着」とは、裾が膝まであるのは「コンビ肌着」と同様ですが、股下にスナップボタンがついていません。
あまり動きが少ない新生児期の頃は、オムツ変えに便利ですが、動きが出てくる生後2ヶ月頃になると、はだけてしまいます。
「長肌着」よりも「コンビ肌着」の方が長い期間着用できるため、我が家は、「長肌着」は購入しませんでした。
腰がすわってくる、7ヵ月以降になると、お座りした状態で着替えることが多くなるため、上からかぶることができる、「ロンパース肌着」がおススメです。
こちらのサイトでは、肌着の選び方が分かりやすくのっていますので、ご参考にしてみて下さい。

赤ちゃん用 ガーゼ
ガーゼは、母乳やミルクの吐き戻しなどの汚れを拭いたり、沐浴(もくよく)時などに使用します。
生後3ヶ月頃になると、よだれがでる量が増えたり、母乳やミルクの吐き戻しも一時的に多くなります。そうなると、スタイ(よだれかけ)の方が便利のため、ガーゼからスタイに移行します。
ガーゼは、顔を拭いたり、お尻を拭いたりするのに使うこともできます。
出産前は5枚程度あれば足りるでしょう。
ベビー用品店では、数枚セットで販売されています。ドラッグストアのベビー用品コーナーにも売っていますよ。

タオル
沐浴(もくよく)する際に、赤ちゃんの体に巻くタオル、そして、洗い終わった後に赤ちゃんの体を拭くタオルが必要です。
また、寝かせる際に直接シーツの上で寝かせるよりも、シーツの上に1枚バスタオルを敷いておくと、汚れたときにすぐに取り換えられ、便利です。
赤ちゃんは、母乳やミルクの吐き戻し、よだれ、おしっこ・うんちなどで汚しやすいため、大人用とは別に赤ちゃん専用のタオルがあった方が便利です。
フェイスタオルは4枚程度、バスタオルは2~3枚あると足りるでしょう。

赤ちゃん用 洗濯洗剤
赤ちゃんは、肌がデリケートです。
大人用の洗濯洗剤では、洗剤の成分が衣類に残り、それが肌に触れた際にかぶれることがあります。
そのため、新生児期~1歳頃までは赤ちゃん用の洗濯洗剤を使用し、洗濯することを勧められています。
とはいえ、最近の洗剤は、こどもから大人まで使える洗剤が多いです。今、使用している洗剤が、赤ちゃんでも使用できるかどうか調べてみて、問題がなければ、そのまま使用して良いと思います。
ベビー用品店やドラッグストアでは、赤ちゃん専用の洗濯洗剤が販売されています。

赤ちゃん用 綿棒
沐浴(もくよく)後の耳掃除や鼻掃除の際に使用します。
沐浴は、退院翌日からやらなくてはいけないため、事前に準備していた方が良いでしょう。
ベビー用品店・ドラッグストアでは、赤ちゃん用の小さな綿棒が販売されています。
大人用の綿棒でも問題はないですが、新生児の耳や鼻は小さいため、赤ちゃん用の方が使い勝手は良いと思います。

赤ちゃん用 爪切り
赤ちゃんの爪を切る、専用の小さなハサミです。
産まれた時から長い爪の赤ちゃんもいますので、出産前に準備していたほうが安心です。
産院では貸し出しできるところが多いので、入院中は持っていかなくても問題ないです。
「赤ちゃんってなんで、こんなに爪が伸びるのが早いんだ」と思うほど、こないだ切ったと思えばすぐ伸びます。
爪を切ることで、顔のひっかき予防にも繋がります。
小まめに使用しますので、準備しておいて損はありません。
最近では、電動ヤスリがついている子供用のネイルケアセットが販売されています。私は使用したことがありませんが、便利そうですよね。
ただ、私は3人とも小さなハサミを使っていて爪切りに困ったことはないので、小さなハサミタイプのものでも十分かと思います。
爪切りは、ベビー用品店やドラッグストアに売っています。

体温計
大人が使用しているもので問題ありませんが、自宅にない場合は購入しておいた方が良いでしょう。
赤ちゃんは、生後半年まで母親の免疫があり、風邪をひきにくいと聞きます。
しかし、我が家の次女は、姉・兄がいるため、出掛ける頻度も多く、生後半年間で2回、感染症にかかりました。
赤ちゃんの体調のバロメーターになりますので、家にあった方が良いです。

赤ちゃん用 保湿剤
育児するまで、赤ちゃんは、いつでもすべすべの肌だと思っていました。しかし、そんなことはなく、赤ちゃんの肌は荒れやすいです。
特に、生後0~2ヶ月程度までは、乳児湿疹(にゅうじしっしん)といって、赤や白のポツポツとした湿疹が顔や首にできやすいです。
大人も子供も保湿が大事なんだと学びました。
沐浴(もくよく)・入浴後の保湿は必須です。それ以外の時間でも、小まめに保湿することが多いです(特に秋冬)
保湿することで、乳児湿疹はもちろん、肌荒れは激減します。
退院後は、すぐに使用しますので、事前に準備しておきましょう。
新生児から使用できる保湿剤がベビー用品店・ドラッグストアで販売されています。
私のおススメの保湿剤はこちらです。べたつきがなく、短時間でサッと塗れます。保湿力も高く、肌トラブルもありませんでした。
 | 「15日 先着で最大1000円OFFクーポン」アトピタ 保湿全身 ミルキィローション ポンプボトル 300ml 価格:1319円 |

ベビーソープ、沐浴剤
退院後は、だいたい翌日から毎日沐浴(もくよく)しなければいけません。そのため、事前に準備しておいた方が良いでしょう。
沐浴の際、赤ちゃんを洗うのに「ベビーソープ」と「沐浴剤」があります。
「ベビーソープ」は泡タイプや石鹸タイプがあります。大人と同じように、洗い流す必要があります。
「沐浴剤」は、洗い流さなくても良い入浴剤です。ベビーバス(沐浴用のお風呂)にお湯と「沐浴剤」を入れ、ガーゼなどで体を洗います。洗い流す必要はありません。
沐浴剤は、基本的には沐浴の期間中でしか使用しません。
また、洗浄力が低いため、汚れを十分に落とすことができないというデメリットもあります。
我が家では、3人とも「ベビーソープ」を使用しました。
沐浴期間が終了しても、お風呂でそのまま長期間使い続けることができます。
ベビー用品店・ドラッグストアで購入できます。
ちなみに、我が子が長年愛用している、ベビーソープはこちらです。
 | 価格:586円 |

湯温計
沐浴(もくよく)する際、適切なお湯の温度(40°前後)になっているのか確かめる必要があります。
そのため、湯温計は必要ですが、お湯の温度を調整できる場合は必要ありません。
また、慣れてくると手の感覚で適温なのかどうかわかるようになります。私自身も産後3週間目あたりになってくると、湯温計は使用しませんでした。
使用期間が短いため、安価なもので良いと思います。
ベビー用品店には、可愛らしい湯温計が売られていますが、お湯の温度が分かるものであれば、なんでもいいと思います。

ベビーバス
沐浴(もくよく)するときに使用する、赤ちゃん用のバスタブです。
こちらも翌日から使用するため、事前に準備が必要です。
ただ、家庭によって異なりますが、使用期間は早くて1ヶ月です。なぜなら、1ヶ月検診で問題がなければ、その後は大人と一緒にお風呂に入れるからです。
我が家の場合は、一度、一緒にお風呂に入ってしまうと、ラクさを覚えてしまい、沐浴が面倒になりました。
もちろん、生後1ヶ月以降も使用でき、3ヶ月くらいまで沐浴している家庭もあります。
どちらにしても、使用期間は数ヶ月単位で短いため、安価なものやお下がりでも問題ないです。
また、ベビーバスは大きいので、空気で膨らむタイプのものをおススメします。
使用しないときは、コンパクトに保管することができ、第2子以降にも使用することができます。
浴室が広いご家庭の場合は、ベビーバスを浴室に置いて、ママやパパが体を洗っている時に待ってもらうように使用することもできると思います。
(ハイハイするようになったら、目が離せないですからね)
腰が据わるようになると(7~8ヶ月頃から)使い勝手は良いと思います。
私が使用して良かったものは、リッチェルの『ふかふかベビーバス』です。
 | 【1種類を選べる】ふかふかベビーバス抗菌K ベージュ(1個)【リッチェル】[お風呂 ケアグッズ ベビーケア おふろ用品] 価格:3110円 |

哺乳瓶
赤ちゃんの栄養方法には、完全母乳・母乳とミルクの混合・完全ミルクの3つの方法があります。
完全母乳と決めていても、最初はなかなか出が悪かったり、小まめな授乳に疲れたりします。また、夜間や産後1ヶ月以降のママの外出の時などに、母乳の代わりにミルクを飲ませたり、母乳を冷凍保管して哺乳瓶で与える方法もあります。
安心材料としても、出産前に哺乳瓶は1本は用意しておいて良いと思います。
新生児のうちから、哺乳瓶に慣れておかないと、いざ哺乳瓶で飲ませようとする時に嫌がってしまいます。
特に、1歳未満で保育園に預ける予定がある場合は、保育園で冷凍母乳やミルクを哺乳瓶から飲ませることになります。
保育園の入園が決まってから、哺乳瓶から飲む練習をするのはかなり大変です。(赤ちゃんが嫌がってなかなか飲みたがりません)
そのため、1歳未満で保育園に預ける予定がある場合は、新生児のうちから哺乳瓶に慣れることをおススメします。
(完全母乳で哺乳瓶の練習をする場合は、夜間のみミルクに切り替える、母乳を冷凍保存して哺乳瓶から飲ませるなどの方法があります)
ちなみに我が子は、長女は完全母乳、長男は混合でしたが生後3ヶ月頃からミルクを拒否したため、それ以降は完全母乳でした。次女は混合です。
私が経験した中で完全母乳の良いところは、離乳食を開始する前までは、体一つで栄養を補給できるところです。外出・外泊時に、哺乳瓶やミルク、洗浄液などの用品を用意をする必要がありません。もちろん、ミルク代もかかりません。
デメリットは、新生児期の頃は頻回の授乳が必要であり、疲れてしまうことです。夜間の授乳も頻回で寝れませんでした。また、赤ちゃんを預けて気軽に出掛けることができない点もデメリットです。出掛けることはできても、次の授乳時間を気にして用事を済ませなければいけません。
ミルクの良いところは、新生児期から3時間置きの授乳で良いことです。母乳と比べて頻回ではないため、体がラクです。また、夜間も完全母乳育児と比べると、よく寝てくれます。
デメリットは、泣いている中でミルクを急いで作らないといけないことや、ミルク代がかかること(1缶3000~4000円程度)、飲み終わった後の洗浄や消毒が面倒なこと(特に夜間)です。
※個人の経験です
哺乳瓶の種類は色々ありますが、こだわりがなければ、安価のもので問題ないです。
我が家は、ChuChuのガラスタイプを使用しています。プラスチックは軽く、万が一落としても壊れることはありませんが、傷がつきやすいです。そのため、ガラスタイプを使用しています。
また、ChuChuのいいところは、安価なのと、乳首が新生児期からサイズアップする必要がないことです。
粉ミルクの種類も様々ですが、産院で使用したミルクが使いやすいと思うので、粉ミルクは出産後に準備しても遅くないと思います(入院中にサンプルでもらえると思います)
我が家は、最初は産院で使用していた「すこやか」を使用していました。しかし、高価なのと、便秘ぎみであったため、「はいはい」に変えました。
哺乳瓶を準備するにあたり、哺乳瓶だけではなく、哺乳瓶を洗浄する洗浄液(今は泡タイプも売っています)、哺乳瓶専用のブラシやスポンジ、消毒用品なども必要になってきます。
哺乳瓶を消毒する方法には、洗浄液に浸けるタイプのものと、電子レンジでチンして消毒するタイプがあります。
電子レンジで消毒する場合は、専用のケースが必要です。
電子レンジの方がお手軽ですが、おもちゃで遊ぶようになってくると(生後3~4ヶ月頃から)おもちゃを消毒することもあります。
その際は、洗浄液に浸して消毒することが多いので、消毒液も後々はあると便利でしょう。
哺乳瓶は、ベビー用品店の方が種類豊富のため、そちらで購入することをおススメします。

オムツ、おしりふき
オムツは必要ですが、買いすぎには注意が必要です。
万が一、用意し忘れたとしても産院で使用したものをそのまま貰えることが多いので、数日は持つでしょう。
新生児期の場合は、「新生児用」が販売されていますので、それを1~2袋買うと良いと思います。
生後1ヶ月を過ぎると、新生児用を卒業し「テープタイプのSサイズ」に移行しますので、買いだめはしないほうが良いでしょう。
また、大きめに生まれた赤ちゃんであれば、すぐにSサイズに移行する可能性もあるため、買いだめには注意が必要です。
ちなみに我が子は、「新生児用」は1ヶ月で卒業しました。また、新生児の間は、オムツは1週間に1袋使用していました。
テープ式のオムツは、「パンパース」、「メリーズ」、「ムーニー」、「グーン」などのブランドがあります。
我が家では、「パンパース」を使用していました。
パンパースは、テープ部分に伸縮性があり、赤ちゃんが動いてもオムツをしっかりフィットさせて取り換えることができるため、おススメです。
漏れも少なく、オムツかぶれもありませんでした。
ちなみに、オムツの値段が安いのは、圧倒的に「西松屋」です。「マツモトキヨシ」も比較的安いです。
おしりふきは、オムツとは異なり、オムツを卒業するまで使い続けることになりますので、ある程度の数を買っておいた方が便利です。
数個セットで販売されていることが多く、段ボール1箱でも販売されています。
おしりふきも「西松屋」で販売されているものがおススメです。

寝具
出産前に、赤ちゃんをどのような方法で寝せるのかを考え、必要な寝具を用意した方が良いでしょう。
我が家の場合ですが、友人からベビーベッドをいただいたので、長女と長男はベビーベッドを使用していました。
次女の時は、ベビーベッドを手放していたため、子供用のベッド(上下左右に柵がついているもの)にベビー用の寝具をひいて寝かせていました。
ベビーベッドのメリットは、たとえ床掃除できない日でも気にすることなく寝かせることができる点です。赤ちゃんがいると、頻回に掃除するのが大変ですからね。
また、第2子以降の場合は、赤ちゃんの安全を守ることができます。上に小さな子供がいると、おもちゃが床に散らばっていたり、気を付けていても赤ちゃんを踏んでしまう可能性があります。
せっかく寝てくれた赤ちゃん。ゆっくり寝かせるためにも、ベビーベッドの方が安心・安全感があります。
また、次女の場合のみですが、生後3ヶ月頃からベッドは寝るところだと理解しているようで、20時頃にベッドで寝かせると、そのまま1人で寝ることが大半でした。
デメリットは、つかまり立ちするようになると、転落する可能性が出てくることです。ぐっすり寝ている時は問題ありませんが、いつの間にか起きていることもあるため、ベビーモニターなどで監視したり、お昼寝している時は小まめに様子を見に行っていました。
また、1歳前後になると、添い寝の方がよく寝てくれます。1歳過ぎると、ベビーベッドは場所もとるため、片付けていました。
子供用に買ったベッドだと、柵がついていて安心感があるのと、大人も添い寝できるため、便利でした。
ベビーベッドは赤ちゃんの時だけの使用ですが、子供用ベッドは将来的に使用できます。部屋のスペースを確保できる場合は、思い切って、子供用ベッドを購入するのもおススメです。
寝具類は、ベビー用の敷布団・防水パット・シーツを購入しました。
枕と掛け布団もついていましたが、それはほとんど使用しませんでした。
春夏は大きめのバスタオル、秋冬はベビー用の毛布を足元のみかけていました。
ベビー用品店では、寝具はセットになって売っていることが多いので、そちらを購入すれば安心でしょう。

チャイルドシート
車を使用する場合は、退院当日から必要になります。
そのため、事前に購入することが必須です。(タクシーでの移動はチャイルドシートを使用しなくても良いです)
チャイルドシートは6歳くらいまで使用します。
数年単位で使用はしますが、高価なものが多いです。また、歳が近い兄弟ができる場合は、2台、3台必要になってきます。
種類も様々であり、どのように選べばよいのか悩んでしまうと思います。
実際に店舗(ベビー用品店)に行って、お店の方に聞いたり、インターネットで調べるのが良いと思います。
安全で、装着しやすく、長く使用できるものをおススメします。有名なメーカーであれば、中古品やお下がりでも問題ないと思います。

生理用ナプキン、生理用ショーツ
出産後、1ヶ月程度は悪露(おろ)といって生理のような出血があります。そのため、昼・夜用のナプキンが毎日必要になります。
多くの産院では、ナプキンを1~2袋程度もらえます。
ただ、それでは足りないです。出産から1ヶ月は使用するため、使い慣れた生理用ナプキンを用意しておいた方が良いでしょう。
生理用ショーツも同様にあった方が安心です。個人差はあると思いますが、特に出産から1週間は出血量も多いため、専用のショーツの方が漏れの心配も少ないです。
生理用ショーツのほかに、「産褥用ショーツ」というものがあります。医師の診察や看護師・助産師の処置の際に、ショーツを脱がなくても良いように、股の部分が開くように設計されたショーツです。
産院によっては、数枚用意して下さいと指示があるかもしれません。
使用期間は、入院中のみですが、その後も「生理用ショーツ」として使い続けることができるため、あって損はないと思います。
ショーツは、ベビー・マタニティー用品店、ランジェリーショップにて販売しています。
ちなみに、生理用ナプキンのほかに、「産褥用パット」というものがあります。
出産直後から1~3日程度(個人差あり)は出血量が多く、生理用のナプキンでは追いつかないです。生理用のナプキンと比較すると、厚みがあり、長さもあって、オムツに近い吸収パットになります。産褥用パットは、だいたい産院でもらえます。使用期間も出産直後から1~3日のため、ご自身で用意する必要はないです。
※産褥とは:出産後、体が妊娠前に戻るまでの期間のことを指します。出産後から6~8週までが産褥期といわれています。

授乳用ブラジャー、母乳パット
授乳用ブラジャーとは、赤ちゃんにおっぱいをあげやすいように設計された、ブラジャーです。マタニティーブラジャーとも言われています。
特に、母乳育児を考えている方は必要でしょう。
普通のブラジャーと比べて締め付けが少なく、快適に過ごせるため妊娠期間から着用することができます。
妊娠中や授乳期間中は、胸が張ったり、サイズが大きくなったりするため、締め付けの少ない授乳用ブラジャー(マタニティーブラジャー)の着用がおススメです。
母乳パットとは、母乳を吸収してくれるパットです。
片方のおっぱいをあげている時、もう片方のおっぱいからも母乳が出てしまいます。
また、授乳していないときでも、赤ちゃんが泣いていたり、ちょっとした刺激で母乳が出てくることがあります。
ふとした時に母乳が出ても、下着や洋服を汚さないように吸収してくれるのが、母乳パットです。
母乳パットは、産院によっては1袋もらえるところもあります。産後もとりあえず、1袋あれば1ヶ月前後は持つと思います。
授乳ブラジャーは、ベビー・マタニティー用品店、ランジェリーショップにて販売しています。
母乳パットは、ベビー・マタニティー用品店やドラックストアで販売しています。
産まれる前にあったら便利なもの 7選

次に、出産前に必ず用意する必要はないのですが、あったら便利なものを紹介します。

ベビー服、ベビー用ハンガー
出産後、1ヶ月間は外出するのは、2週間検診か1ヶ月検診くらいです。
寒い時期は、室内でもベビー服が必要ですが、気温が高い時期は、自宅・もしくは肌着で過ごすことがほとんどです。
地域や時期によると思いますが、生後1~2ヶ月も経つと季節が変わったりします。そして、赤ちゃんも成長します。
何枚も買ったけど、すぐに暑くなって(もしくは寒くなって)着られなくなることがあります。
50~60cmのベビー服はあっても2~3枚で良いです(個人的見解ですが)

スタイ
新生児期は、スタイよりもガーゼの方が使用します。
生後2~3ヶ月頃になると、よだれや母乳・ミルクの吐き戻しが増えるため、スタイの方が便利です。
出産後、すぐにスタイを使用するわけではないので、出産後に購入しても遅くはありません。
また、出産祝いの贈り物として選ばれるのが多いのが、スタイです。ご自身で購入しなくても十分に足りたという場合もあります。
赤ちゃんのよだれの量によりますが、3~5枚ほどあれば足りると思います。

ベビーカー
必ず必要ではありませんが、あると便利なベビー用品です。
ベビーカーも出産後、すぐに使用するわけではないので、産まれてから購入しても遅くはありません。
特に、徒歩での移動が多いご家庭には重宝します。また、広い公園や施設へのおでかけ、レストラン等にあると便利です。
スーパーやショッピングモールには、生後2ヶ月頃から使用できるベビーカーが置いてあるため、上記に当てはまらない場合は、様子を見てから購入するのも1つです。
コンパクトに収納できるベビーカーも増えてはいますが、それでも保管に場所はとります。
また、他のベビー用品と比べても高価のため、吟味して選ぶ必要があります。
我が子は、1~2歳頃は一時期ベビーカーに「座りたくない」と、嫌がる時期がありました。しかし、2歳半過ぎると今度は「歩きたくない」と嫌がるため、一時的に使用はしなかったものの、結果的には長く使用しています。
だっこ紐だけの移動では、体が大変ですので、状況に合わせて使用するのがおススメです。

だっこ紐、スリング
だっこ紐は、自宅内・外出先など時間・場所を問わず活躍することが多いです。
ベビーカーの場合は座らせると嫌がる子もいますが、だっこ紐を嫌がる赤ちゃんはあまり聞いたことがありません。
特に、赤ちゃん連れで大人1人で買い物に行く際は、だっこ紐は必須です。
値段もピンからキリで、種類も豊富のため、選ぶのに多少の時間がかかります。そのため、時間のある出産前に購入するほうが吟味して選ぶことができます。
メーカーや物によっては、生後まもなくから使用できる物もあります。
ただ、新生児期のころは使用しないことが多いため、必ずしも出産前に必要というわけではありません。
インターネット上でも購入できますが、店舗で実際に使用して選ぶ方をおススメします。
エルゴベビー、ベビービョルンなどのブランドが有名です。
こちらのサイトでは、だっこ紐の口コミをランキング形式に詳しく紹介しているので、参考にしてみて下さい。
ちなみに我が家は、エルゴベビーを使用しています。
だっこ紐のほかに、「ベビースリング」というグッズがあります。赤ちゃんを抱っこする時に使用するという点では、どちらも変わりないです。
だっこ紐は、両方の肩にベルトがついていますが、スリングは、片方の肩のみにベルトをかけて吊るし赤ちゃんを包むような形で抱っこができます。
抱っこ紐と比べると、コンパクトに収納ができ、重量も軽いです。また、赤ちゃんをより密着した状態で抱っこができるため、よく寝てくれるという口コミがあります。
私自身、スリングは使用したことがありません。だっこ紐でもよく寝てくれたため、購入する機会はありませんでした。
ただ、だっこ紐は、肩や腰に負担がかかるのと、持ち運ぶ際にかさばります。
どちらもメリット・デメリットがあります。お母さん・お父さんが使いやすいものを選ぶのが良いと思います。また、スリングは、だっこ紐と比べると安価のため、どちらも購入し、使い分けるのも手だと思います。

ハイローチェア、バウンサー
ハイローチェアとは、赤ちゃんを寝かせることができる、簡易的なベッドのようなものです。
ベビーベッドと比べると、コンパクトであり、下にキャスターがついているため、移動させることができます。
また、高さの調整ができ、リクライニング機能もあります。そのため、寝かせるだけではなく、体を起こして椅子のように使用することもできます。(テーブル付きのハイローチェアが多いです)
ハイローチェアの最大のメリットは、揺らすことができるところです。赤ちゃんは、揺れているとよく眠ってくれます。(大人も電車などで揺れていると、つい、ウトウトしちゃいますよね)
常に、泣いている赤ちゃんを抱っこして揺らしているのは大変です。トイレにも行けない、食事も取れない…ということにならない為に、ハイローチェアの活用がおススメです。
もちろん、新生児期から使用できます。というよりも、一番活躍するのは、新生児期だと思います。
必ず必要な育児用品ではありませんが、赤ちゃんがよく寝てくれるので、あると便利なのは間違いありません(家電で例えると、自動掃除機や電気調理器、乾燥付き洗濯機のようなものです)
デメリットは、高価であること、場所をとること、使用期間が限られていること(1年未満)です。
赤ちゃんは、だんだん大きくなってきますので、いつまでもハイローチェアで寝かせるのは難しくなります(だいたい、寝返りをし始める4~6ヶ月頃から難しくなるかと思います)
しかし、場所は取りますが、テーブル付きの背もたれ椅子として活用できるため、ベッドというよりも椅子として使えば、長く使用できます。
また、私のおススメは、電動で揺らす機能がついているハイローチェアです。手動と比べると、さらに高価にはなりますが、手動だと寝るまで誰かが動かさなければなりません。その点、電動であれば勝手に揺れてくれるため、椅子を動かす手間が省けます。
椅子として活用できても、使用期間は限られていますので、中古品やレンタルでも問題ないと思います。
一方、バウンサーは、上下に揺れる椅子のようなものです。赤ちゃんを寝かせるためのグッズというよりも、赤ちゃんをあやす椅子のおもちゃです。
泣いている赤ちゃんをバウンサーで揺らすと、泣き止み、キャッキャッと笑ってくれます。初めは、誰かが揺らす必要がありますが、慣れてくると赤ちゃん自身が体を動かして、揺らすことができます。
ハイローチェアと比べると、安価であり、軽量のため、持ち運びも可能です。
デメリットは、ハイローチェアと比べると、さらに使用期間が短いことです。新生児期~寝返りができるまでです(対象年齢は2歳までになっています)
ハイローチェアのように、食事の際の椅子として代用するのは難しいため、どうしても使用期間が短くなってしまいます。
私は、ハイローチェアを購入しました。3人とも使用しましたが、あってよかった育児用品です。(ただ、手動だったので、電動をおススメします)

鼻水吸引器
赤ちゃんの鼻水を吸ってくれる器具です。
出産前に用意する必要はありませんが、後々風邪をひいた時にあったら便利なグッズです。
赤ちゃんは、風邪をひいたとき、鼻の構造上、鼻水が詰まりやすいです。もちろん、自分で鼻をかむことはできません。鼻がつまっていると、うまく授乳できなかったり、寝れなかったりします。
そんな時、赤ちゃんの鼻水を吸うことで、授乳や睡眠がスムーズになります。また、症状が早く回復しやすいと言われています。さらには、正しく使用することで、中耳炎や副鼻腔炎を予防することもできます。
鼻水吸引器には、大人が口で吸ったり、手で押して鼻水を吸う手動タイプのものと、電動タイプのものがあります。
電動にも、持ち運びができるコンパクトなタイプと、病院にあるような据え置きのタイプのものがあります。
手動タイプは、ベビー用品店やドラッグストアで販売しており、手軽に購入できます。また、電動タイプと比べると安価なものが多いです。
持ち運びも可能であり、洗浄も簡単です。
デメリットは、使用するのに慣れが必要なことです。
赤ちゃんの鼻にチューブの先を当てながら、同時に口や手を使って吸い取る必要があります。赤ちゃんが激しく動いてしまうと、うまく吸い取ることができません。そのため、手足や頭を固定する必要があり、そうなると手が足りません。
私自身も使い慣れるまで時間がかかりました。
赤ちゃんの動きがまだ少ない時期は、お手軽に使用できますが、ある程度大きくなり、動きが激しくなると、なかなか難しいでしょう。
また、どのくらいの強さで吸えばよいのかよく分からないのと、吸引力が弱い点もデメリットです。サラサラとした鼻水は簡単に吸えますが、粘着性がある鼻水は、なかなかうまく吸えません。
一方、電動タイプは、鼻先にチューブを当て、電源を入れるだけで自動的に吸引してくれます。非利き手で赤ちゃんの頭を固定し、利き手でチューブを鼻に当てるだけです。
また、吸引力も手動に比べると強いです。特に、据え置きタイプは吸引力が強く、よく鼻水がでるお子さんには重宝すると思います。
ハンディータイプは3500~4000円程度、据え置きタイプ(メルシーポット)は10000円前後と、手動タイプと比べると高価です。
しかし、その分、よく吸い取ってくれます。手動タイプと同様で、ハンディータイプは洗浄も比較的簡単です。
据え置きタイプは、吸引力の調整ができます。ただ、洗浄は手動タイプやハンディータイプと比べると面倒でしょう。
我が子は、3人とも鼻水が頻繁に出るタイプではないため、ハンディータイプのものを購入しました。私のおススメはこちらの商品です。私自身もインターネット上で購入しました。
 | 価格:3480円 |

乳頭クリーム
乳頭クリームとは、名前の通り、乳頭を保護するクリーム状の保湿剤です。
母乳育児を考えている方は、出産前に用意しておくと便利だと思います。
なぜなら、一番必要な時期が産後直後だからです。ちなみに、母乳育児を考えていない方は必要ないです。
産まれてから2~3週間程度(個人差あり)は、赤ちゃんがおっぱいを吸うことに慣れていないこともあり、お母さんの乳首が切れやすくなります。そうすると、赤ちゃんが乳首をくわえるたびに激痛が走るのです。
ただでさえ、体がツライ産後。授乳のたびに乳首が痛くて、それがかなりのストレスになります。
そんな時に使用するのが、乳頭クリーム。赤ちゃんが舐めても問題のない成分でできており、お母さんの切れた乳首を保護してくれます。
これを塗るか、塗らないかだけで、本当にだいぶ違います。
個人差はあると思いますが、産後1ヵ月もすれば、赤ちゃんもおっぱいを吸うのに慣れ、乳首が切れることもないので、痛みがなくなります。
使用期間は短いのですが、今度は歯が生え始めた時期に、乳首を歯で噛まれて切れることがあります。その時にも使用できるので、使わなくなってもそのまま取っておいて下さいね。
私の場合、3人とも乳首が切れて、痛い思いをしました。そんななか、乳頭クリームを塗布すると、傷も早期になおり、産後3週間くらい経つ頃には、ストレスなく授乳ができました。
実は、1人目の時は、必要性が分からず購入しませんでした。しかし、産後、頻回の授乳で乳首が切れてしまい、助産師さんに勧められて産院でクリームを購入しました。店頭で購入した方が安かったので、「買っておけばよかったな」と逆に後悔しました。
乳頭クリームはいろいろな種類があり、どれにしようか迷ってしまいます。
ちなみに、私が助産師さんに勧められて3人とも使用した乳頭クリームはこちらです。
 | ピジョン リペア二プル 10g 2本入【正規品】【k】【ご注文後発送までに1週間前後頂戴する場合がございます】 価格:1416円 |
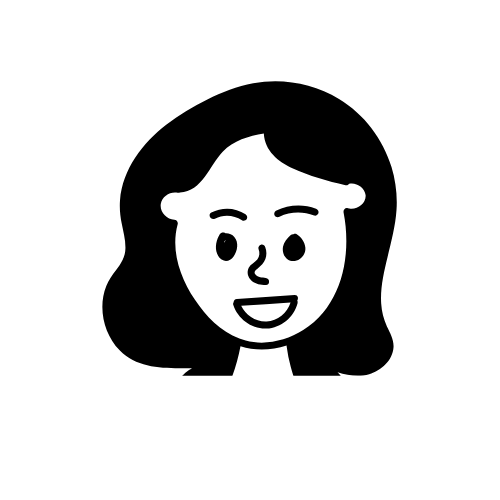
以上が、私流出産準備リストです。
私自身、赤ちゃんができてから、初めて知る育児用品がたくさんありました。
また、長女と次女が6歳差なのですが、6年も経過すると長女の時にはなかった、便利な育児用品が増えていました。
初めての育児はとにかく大変。便利な育児用品を利用して、うまく手を抜いていきましょう。